高校の推薦入試や大学の推薦入試では面接の他に小論文を求められることがあります。
小論文と聞くと難しく聞こえるかもしれませんが、決して難しいものではありません。
小論文とは何か、小論文の書き方はどうすればいいのかを理解すれば、小論文は書くことが出来ます。
この記事では小論文のイメージと、その書き方を説明していきます。
特に小論文の試験を控えている中学生や高校生は参考に御覧ください。
そもそも小論文とは・・・
小論文を書き始める前に、そもそも小論文とは何かということを理解する必要があります。
小論文を理解するときに比較するものが作文です。
皆さんは作文と小論文の違いは分かりますか?
作文とは日記のようなもので、何かがあったことや起こったことを書く、また思ったことを書きます。
何も考えずに出来事を記録していく日記のようなものが作文になります。
それに対し小論文とは自分の考えを理由とともに説明し、読み手を納得させる文のことです。
ただ物事を書けばいいという訳ではありません。何か事柄に対し自分の意見や考えを提唱し、なぜそう思うのかという理由をしっかりと説明することが重要です。
つまり小論文で大事なことは、自分の考えとその理由です。
この2つが小論文の肝になります。この2つをしっかりと抑えることが出来れば、小論文を理解することに繋がります。
次の2つの高校の入試問題を比較しましょう。
東京都立飛鳥高校(作文)
自分と意見が違う人と協力するためにはどのようなことが必要だと思いますか。自分の経験をもとにして書きなさい。
東京都立両国高校(小論文)
あなた自身の経験の中で、公共の場でのマナーについて問題があると感じた例を一つ挙げ、その問題を解決するためにはどうし たらよいか、そう考える理由も含めて具体的に書きなさい。
これらは実際に東京の高校入試で出題された試験内容です。
飛鳥高校では作文、両国高校では小論文が求められます。
したがって飛鳥高校の作文の問題では思ったことを書く、一方で両国高校の小論文では自分の意見とその理由を述べましょう。
もちろん作文において理由を説明しても問題はありません。
※上記の様な問題は東京都教育委員会のホームページで公開されています。
平成27年度東京都立高等学校入学者選抜における推薦に基づく選抜で実施した集団討論、小論文・作文、実技検査のテーマ等一覧
小論文の書き方

それではこれから小論文の書き方を説明していきます。
小論文はいくつかの書き方や構成がありますが、ここでは一番基本的な書き方について説明します。
ルールを事前に確認

まず小論文を書く前に、その小論文で求められるルールを事前に確認しましょう。
小論文も含め、入試問題には必ずルールが存在します。
入試の場合は解答欄以外の余白には何も書いてはいけない、問題用紙は持ち帰らない、時間が来たら回答をやめるなどです。
小論文では特に字数に関するルールや、自分の経験を含めるというルールが多いです。
実際に高校入試で出題された問題を見ていきましょう。
次の問題は平成27年度の東京都の蒲田高校で出題された問題です。
●学校スローガンの「集い、鍛え、伸ばす」の 「集い」にかかわって、学校という場で集団 で学習することが有利な点について、自分 の経験に絡(から)めて意見を述べる。(500字以内)
このテーマを見た時に、守らなければならないルールが3つあることが分かります。
まずは与えられたテーマの有利な点を書くことです。
ただ学校で学習することを述べればいいわけではありません。
学校で学ぶことの有利性に触れながら文を作っていきます。
また有利な点だけを述べるのではなく、不利な点と対比しながら書き進めるのも効果的です。
2つ目のルールは自分の経験に絡めて意見を述べることです。
自分の考えだけで論じ進めてはいけません。
そこにしっかりと自分の体験を組み込んでやることが求められます。
そして3つ目のルールは500字以内で述べるということです。
いくらいい内容の小論文でも、定められた字数を少しでもオーバーすれば、それは絶対的にアウトです。
また逆に字数が少なすぎてもアウトです。
もし最低字数が指定されていない時は、制限文字数の8割から9割を目安に字数を設定しましょう。
小論文の構成は起承転結
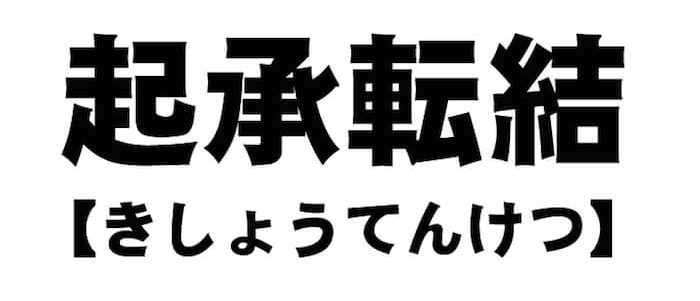
小論文の構成は起承転結の形にすると、書き手も書きやすいでいすし、読み手側も読みやすくなります。
起・・・問題提起
まずは書きたい小論文のテーマから問題提起を行いましょう。
「はたして・・・は~だろうか。」という形で、読み手に疑問を投げかけるようなイメージです。
承・・・現状や一般的な見解
起で設定した問題提起に対して、現状や世間一般的な考え、見解を説明します。
ここはあくまでも主観ではなく客観的な考えです。
一般の人々はどう思っているのか、また一般的にはどう認識されているのかを述べます。
転・・・承に対する自分の考えとその理由
小論文ではここが一番の重要ポイントになります。
起で問題提起をし、承で現状の説明をした上で、そこに自分の意見や考えを述べます。
そして自分の意見を述べた上で、その考えをもった理由を説明します。
ただ説明するだけではありません。
読者を納得させるように理由を説明する必要があります。
よく論理的に説明するとはこのことです。
しっかりと理由をもって説明をすることがとても重要になります。
結・・・結論、起承転の要約
最後は締めです。
今まで述べてきたことを簡単に要約して、それで小論文の終了です。
書き始める前に構成を考える

上記で小論文の書き方を説明してきましたが、小論文を書く前に意識してほしいことがあります。
それはまず小論文の構成を考えるということです。
作文や小論文となると、字数を稼ごうという意識が働き、いきなり書き進めようとする人が多いのです。しかしそれはナンセンスです。
もし途中まで書き進めたところで、やっぱりあの箇所に付け加えようと思ったら、それまで書いてきた内容を消すことになり、とても効率が悪くなり、また紙も汚くなります。
そういったことが起こらないように、まずは小論文の構成を考えましょう。
起承転結の文字数の割合や、書くことを大まかにまとめましょう。
まとめ
この記事では小論文の書き方を説明してきましたが、いかがでしたでしょうか。
もちろん小論文はこの記事で説明した以外の書き方もあります。
しかし何事もそうですが、まずは基礎を身につけることが一番です。
まずは基本的な小論文の書き方を身につけ、それから可能であれば自己流の書き方を見つけましょう。
そして小論文では自分の意見とその理由をしっかりと説明することに意識をおいて書き進めましょう。
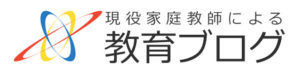






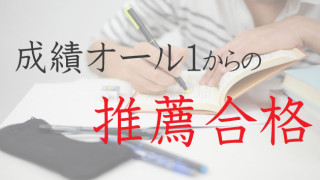
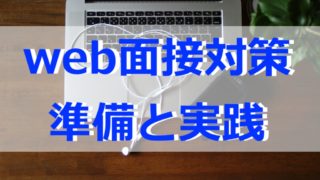


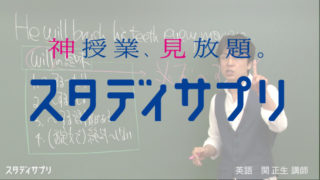

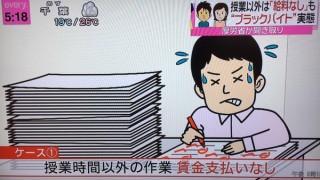


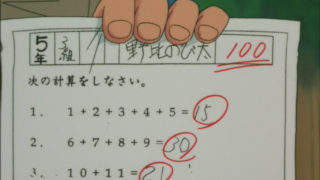

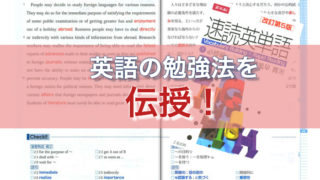

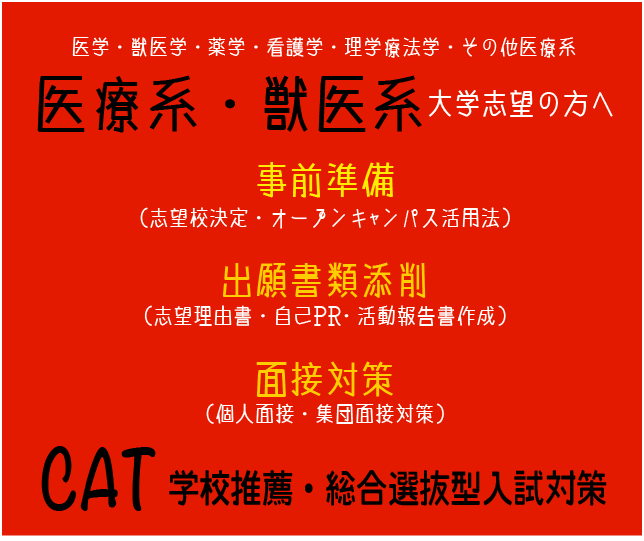
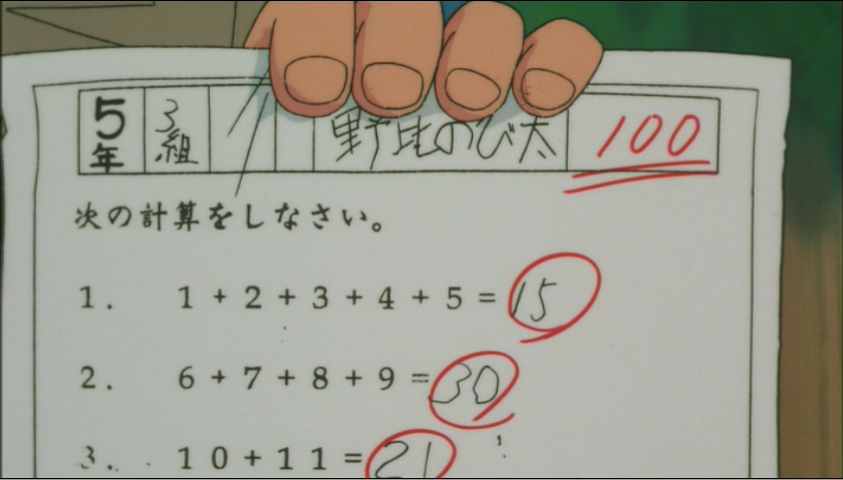

コメント